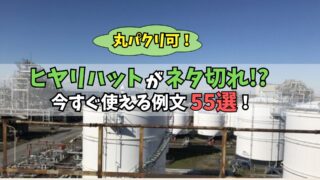ヒヤリハットが思いつかない!!
ヒヤリハットって、毎回提出しているとすぐにネタ切れしがちですよね?
・思いつかないのに書けと言われる
・同じことを書き続けていると怒られる
・変な書き方をすると怒られる
とはいえ、いちいち考えるのが面倒…
しかし、ここではヒヤリハットの対策を考えるコツとパクリOKな例文をご紹介します!
これを読めば、1年間は困ることはなくなるでしょう!
もちろん丸パクりOKです!
もう社長の奴隷になる必要はない!
会社への依存を脱却した集大成がここにあります。
\脱サラリーマンの集大成/
目次
ヒヤリハット事例と対策集(日常&工場)

日常の事例10選
事例1~3【交通事故】
・車線変更時、死角にいた車両に気づかず接触しかけた
原因:サイドミラー・目視確認の不足。
対策:車線変更時は目視確認を徹底するよう現場で教育。運転中の「ながら行動」を禁止する。
・自転車運転時、スマホの通知に気を取られたところ、歩行者にぶつかりそうになった
原因:ながら運転による前方不注意
対策:自転車走行中はスマホをリュック、カバンに入れる。朝礼で通勤指導を実施する。
・信号が赤に変わる直前、無理に交差点に進入しそうになった
原因:スピードの出し過ぎで制動距離が長くなった。
対策:制限速度を厳守するよう、営業所内で再教育。過去の事故事例を朝礼で周知。
事例4~6【動作の反動・無理な動作】
・重い物を持ち上げた際腰を痛めかけた
原因:正しい持ち上げ動作ができていなかった。
対策:腰を痛めない持ち上げ方を教育。30kg以上の重い荷物は台車使用や2人作業をルール化。
・高い棚に手を伸ばして荷物を取ろうとし、バランスを崩し転倒しかけた
原因:無理な姿勢での作業。踏み台を使わなかった。
対策:各通路ごとに踏み台や脚立を常備し、背伸びする必要がある高さの場合は必ず使用する。
・ねじを締める際にドライバーが外れて手に当たりそうになった
原因:ドライバーの嵌まりが不十分な状態で締めようとした。不安定な体勢での作業をしていた。
対策:ドライバーがねじ山に嵌まっているのを確かめてから締めるように、現場で周知、教育する。
事例7~10【転倒】
・床に落ちた書類に気づかず踏みそうになった
原因:足元の確認不足、落下物の放置。
対策:書類や物品の即時回収を習慣化する。落ちやすい場所に書類を置かないルールを定める。
・段差に気づかずにつまずいた
原因:段差の表示が不十分だった、暗くてみづらかった。
対策:段差には目立つ色のテープや表示を貼付する。追加で照明を取り付ける。
・雨天時に玄関マットがずれており、滑って転びかけた
原因:ずれやすいマットを使っていた。通行者がずれたマットを直さなかった。
対策:マット裏に滑り止めシートを設置し、雨天時にはこまめに位置確認を行うよう従業員に周知。
・作業エリアに置かれたスパナを踏み、転倒しそうになった
原因:使用後の工具をその場に置いたままにしていた。通路と作業エリアの区別が不明瞭だった。
対策:工具置き場を明確に区画表示し、使う工具以外は都度戻すルール化。
工場の事例21選

事例1~3:【はさまれ・巻き込まれ】
・グラインダー使用時に手袋が巻き込まれかけた
原因:回転機械の使用時に手袋を着用していた。ルールの周知、教育不足。
対策:回転機械の使用時には手袋を外すルールを朝礼で再周知。現場巡回の強化。
・重い扉を閉めるとき、不注意で手を挟みそうになった
原因:扉を閉めるときに目を離していた。油断していた。
対策:扉の開閉時は必ず取っ手部分のみを持ち、手指を挟まない位置に保つ。扉が閉じるまで確認してから目を離す。
・機械の点検中、電源が入っていることに気が付いた。
原因:新人が作業手順を守らなかった。教育が不徹底だった。
対策:点検時は必ず電源をOFFにするよう再教育。ロックアウト・タグアウトを徹底する。
事例4~6:【激突され】
・クレーン作業中につり荷が作業者に激突しそうになった
原因:作業員が吊荷の移動範囲に近づいていた。作業区画が不十分だった。
対策:当該ヒヤリの事故事例を現場で周知。作業範囲を完全に囲うように作業区画を設置する。
・フォークリフトが急に曲がってきて、ぶつかりそうになった
原因:フォークリフトが一時停止を無視した。歩行者が書類を見ながら移動していた。
対策:歩道とフォークリフトの通路をカラーコーンで物理的に分ける。構内のながら歩行に対する注意表示を掲示する。
・構内をよそ見の車が走ってきて、激突されそうになった
原因:歩道の車道よりを歩いていた。運転者が脇見をしていた。
対策:構内ルールを順守しない業者は元請けに報告する。歩道であっても、車道から離れたところを歩く。
事例7~9:【やけど】
・熱した鉄板を素手で触りかけた
原因: オーブンから取り出した直後の鉄板の温度を確認せずに、常温と思い込んで素手で運ぼうとした。
対策:調理場での鉄板、鍋、釜等の持ち運びには、保護手袋の着用を義務化する。
・湯せん中の鍋に顔を近づけた際、蒸気でやけどしそうになった
原因:蒸気の発生タイミングと熱範囲の予測が甘かった。
対策:湯気の向きや広がりに注意を払い、顔を近づけすぎないことを教育。
・スチーム配管にうっかり手を掛けてしまい、やけどしそうになった
原因:高温配管が通っていることを忘れていた。油断していた。
対策:高温の配管は耐熱テープでマーキングする。直接触れないように金網を巻き付ける。
事例10~12:【感電・火災】
・コンセントに濡れた手で触れそうになった
原因:水場での電気機器使用に対する危険意識の欠如。
対策:「乾いた手で操作」ルールの明示と、感電防止教育の実施。ゴム手袋での作業を推奨。
・ケーブルが断線したまま使用しそうになった
原因:ケーブル点検を行っていなかった。破損を放置していた。
対策:1か月に1回電源コードの点検を義務化する。破損ケーブルはすぐに回収・廃棄する。
・トースターの下に可燃物を置いたまま加熱し、発煙しかけた
原因:機器の近くに可燃物を無意識に置いていた。配置管理が甘かった。
対策:加熱機器周辺には可燃物を置かないルールを設定する。「高温注意」の表示を貼る。
事例13~15:【切れ・こすれ】
・ダンボールを開封中にカッターが手に当たりかけた
原因:片手で無理に開封していたため、刃の角度が不安定だった。
対策:カッターの正しい使い方を周知する。手袋の着用をルール化する。
・鋭利な部品のバリで指先を切りそうになった
原因:バリ取り処理がされていなかった。手袋未着用だった。
対策:バリが発生する部品は必ず手袋を着用するよう、現場で教育。手袋未着用者は作業させない。
・狭い通路で壁に腕がこすれ、肌を擦りむいた
原因:通路幅が狭く、身体の一部が接触しやすい状態だった。
対策:作業時は長袖を着用し腕まくり禁止、ぶつかりそうな壁には保護クッションを設置。動線の見直しも検討。
事例16~18:【清掃・修理時】
・清掃中のモップに足を取られて転倒しかけた
原因:作業中の道具の管理が不十分で、通路に放置されていた。
対策:使用中の道具は安全な位置に置くルールを徹底。通行の妨げになる位置には置かない。
・機械清掃中、誤って通電させそうになった
原因:メンテナンス中であることの明示が不十分だった。
対策:清掃・点検中は「作業中」タグを設置し、他の作業者とのダブルチェックを実施。ロックアウトの導入を検討。
・エアコンの掃除中に脚立が不安定で転倒しかけた
原因:床面が傾いていた/脚立の設置が不安定だった。
対策:角度調整が可能な脚立を使用する。可能であれば補助者をつける。脚立使用時のルールも再確認。
事例19~21:【重量物の運搬時】
・重量物を一人で持ち上げ、腰を痛めかけた
原因:一人での作業を優先した。体の使い方も誤っていた。
対策:重量物は原則2人以上で運ぶ。もしくは台車・リフターなどの補助器具を活用する。
・運搬中に荷物が前方視界をふさぎ、他者とぶつかりそうになった
原因:積載量が多すぎて視界が遮られた。周囲確認が不十分だった。
対策:視界を確保できる量で運ぶ。難しい場合は台車を使用するか2人作業にする。
・荷物を床に置く際、手を挟みそうになった
原因:床面との距離感を誤り、手の位置に注意がなかった。
対策:荷物は足の甲・手指の位置に注意してゆっくり下ろす。荷下ろし時の姿勢をマニュアル化する。
ヒヤリハットとは

ヒヤリハットとハインリッヒの法則
「事故には至らなかったが、一歩間違えれば事故につながったかもしれない事例」のこと
安全管理でよく使われる「ハインリッヒの法則」では、1件の重大事故の背景には29件の軽微な事故、そして300件のヒヤリハットがあると言われています。
つまり、ヒヤリハットを減らすことが、重大事故を減らすことになるという考え方です。
ヒヤリハットの原因
・気のゆるみ・近道行為:決められた手順を省略しようとしたときに起きがちです。
・疲労:集中力が切れて注意が散漫になる時間帯や体調不良時に多く見られます。
・情報共有不足:作業の変更や注意事項が共有されていないと、危険に気づけないことがあります。
・知識やスキル不足:新人作業者に起こりやすく、教育やOJTの重要性が問われます。
ヒヤリハットの対策

ヒヤリハットを見つけるにはKY(危険予知)の活用が有効!
ヒヤリハットは、危険予知(KY)を組み合わせると見つかるようになります。
KYは、作業前に「この作業にどんな危険があるか?」をチームで話し合い、予測し、対策を立てる安全措置です。
KY活動がヒヤリハットの発見に直結するため、そのままヒヤリハット報告書に書くことができます。
まとめ:コツを掴めないうちは、パクることで事例をしることができる。

ヒヤリハットの報告や提出は、最初のうちは事例のコツが掴めず、どう書けばいいか迷うことも多いです。
しかし、実際にあったケースや他人の報告から学ぶことで、「自分の現場では何が起こり得るのか?」という視点が育ちます。
将来的には自分で気づき・予測できる力にもつながります。
慣れるまでは、業種別・事例別の例文を見ながら、自分の作業に近いものを置き換えていくのがポイントです!
事故災害のプレッシャー、耐えられますか?
現場は事故災害を起こした時のプレッシャーが他の業界よりも大きいです。
いつか人にけがをさせてしまったら…
と考えると怖いですよね?なら、現場から離れることを検討してもいいかもしれません。
現場出身でもできる仕事(副業)は世の中にたくさんあるんです。
本業以外の収入源は必要、そんなことはわかっている。
問題は、色々探したのに ”自分に合った副業がまだ見つかっていない” ということ。
これは私自身がこれまで何度も迷走してずっと悩んできたことでした。
今では、いろんな迷走、経験があるからこそできる、自分に合った副業を見つける新サービス「副業のセカンドオピニオン」をお届け中。
「脱サラするぞ!!」と鼻息荒くしてまで副業に取り組みたいわけでもない。
本業を維持しながら、着実に副収入を稼ぐ。
そのための具体的な手段に出会うのは簡単、以下ボタンにある公式LINEに登録をいただくことです。
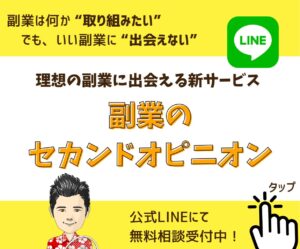
それはまるで、お医者さんのように、丁寧に状況をヒアリング、適切な副業のアドバイス・・
いつ閉じるかもわからない無料サービス、ぜひ体験してみてください。
私エンキャリは今日も必死こいて仕事を頑張るサラリーマンの味方です!!